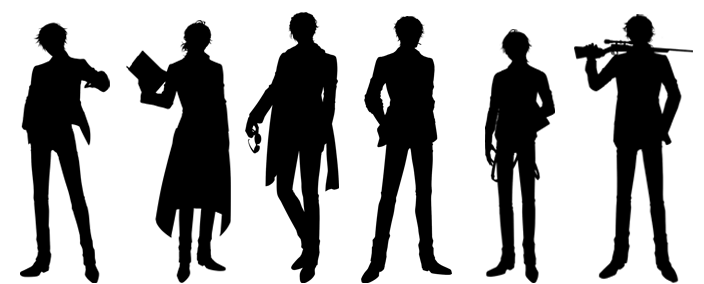
Apr.7 Ryo
珍しく寝起きの悪い朝だった。ぼんやりとした意識をシャワーで覚醒させて、白いシャツに袖を通す。
愛用のワックスでまだ少し湿り気の残る髪を撫でつけスーツのジャケットを羽織ると、鏡にはいつも通りの俺がうつっていた。寝起きの名残はもう無い。
「よし」と言葉にはせず頷いて、俺は玄関のドアを開いた。清涼な朝の空気が気持ちいい。エレベーターはすぐに到着したが、乗り込もうとしたところで俺は足を止めた。
ひらりと、小さな淡い色味が視界を過ぎる。反射的に掴むと、それは桜の花びらだった。
「どこから……」
掌に花弁を乗せたままマンションの下に目をやる。すると向かいにある民家の庭で満開の桜が風に揺れていた。
いつのまにか訪れていた春の景色に少しばかりの笑みが零れる。
「気づいてたか?」 週末に泊まりに来ていたお前の姿を思い浮かべながら、俺は滅多に使わない携帯のカメラに満開の桜をおさめた。
愛用のワックスでまだ少し湿り気の残る髪を撫でつけスーツのジャケットを羽織ると、鏡にはいつも通りの俺がうつっていた。寝起きの名残はもう無い。
「よし」と言葉にはせず頷いて、俺は玄関のドアを開いた。清涼な朝の空気が気持ちいい。エレベーターはすぐに到着したが、乗り込もうとしたところで俺は足を止めた。
ひらりと、小さな淡い色味が視界を過ぎる。反射的に掴むと、それは桜の花びらだった。
「どこから……」
掌に花弁を乗せたままマンションの下に目をやる。すると向かいにある民家の庭で満開の桜が風に揺れていた。
いつのまにか訪れていた春の景色に少しばかりの笑みが零れる。
「気づいてたか?」 週末に泊まりに来ていたお前の姿を思い浮かべながら、俺は滅多に使わない携帯のカメラに満開の桜をおさめた。
Apr.8 Rei
「あちゃ〜、タイミング悪かったな……」
その場にオレの独り言だけが虚しく響く。頼まれていた鑑定の結果を届けに来たのに、特広のオフィスはもぬけの殻。たぶん緊急案件で出払っているのだろう。
「これは出直すしかないかな」
オレがラボを空けていてもお構いなく、デスクの上に適当に鑑定依頼を積み上げていけばいいと思っている特広(ここ)の連中と違って、鑑定結果は依頼主に詳細を口頭説明した上で書類を引き渡し、確認印をもらうのが鑑定課の決まりだ。
いい加減電子決済を導入すればいいのにとずっと思ってはいるけれど、現状このアナログな工程を通らない限りオレの仕事は終わらない。
「……あ、そうだ」
さっさと諦めて踵を返しかけてから、オレはふと思い立ってキミのデスクに歩み寄った。白衣のポケットから取り出したのは、今朝行きつけのカフェで見つけた桜フレーバーのチョコレート。
「お疲れ様」
ハートマークを添えた付箋へのメッセージとチョコレートを残して、オレは特広のオフィスを後にした。
その場にオレの独り言だけが虚しく響く。頼まれていた鑑定の結果を届けに来たのに、特広のオフィスはもぬけの殻。たぶん緊急案件で出払っているのだろう。
「これは出直すしかないかな」
オレがラボを空けていてもお構いなく、デスクの上に適当に鑑定依頼を積み上げていけばいいと思っている特広(ここ)の連中と違って、鑑定結果は依頼主に詳細を口頭説明した上で書類を引き渡し、確認印をもらうのが鑑定課の決まりだ。
いい加減電子決済を導入すればいいのにとずっと思ってはいるけれど、現状このアナログな工程を通らない限りオレの仕事は終わらない。
「……あ、そうだ」
さっさと諦めて踵を返しかけてから、オレはふと思い立ってキミのデスクに歩み寄った。白衣のポケットから取り出したのは、今朝行きつけのカフェで見つけた桜フレーバーのチョコレート。
「お疲れ様」
ハートマークを添えた付箋へのメッセージとチョコレートを残して、オレは特広のオフィスを後にした。
Apr.9 Arlen
髪から滴る雫を払い落とし、真白いガウンに袖を通す。バスルームのドアを開いてリビングに戻ると、テーブルの上には書類の束とよく冷えたミネラルウォーターのボトルが置かれていた。
この部屋に自由な出入りを許している人間は少ない。私がシャワーを浴びている間に訪れたであろう番犬は、この場で主人を待つよりも気を利かせて早々に立ち去ることを選んだらしい。
「相変わらず有能だな」
ボトルを開け、乾いた喉を潤しながら書類の束に目を通す。たまに大雑把な部分が顔を覗かせることもあるが、仕事の早さにおいて彼に勝る者は少なくともこのハウス内には存在しない。
目を通し終えた紙束をテーブルに戻し、ボトルを手にしたまま窓の外に目を向ける。ガラスの向こう側の世界は、オレンジの光に満たされていた。
この一瞬だけを切り取るのならば、早朝にも同じ光景を見ることはできる。だが、私は夜へと変わるこの時間の方が好きだ。オレンジ色の後に訪れる白く清浄な陽の光は、私には眩しすぎるのだから。
「……ふっ」
人知れず笑みを漏らし、ボトルの中身を飲み干した。今夜もまた闇に紛れ、ビジネスの場へと向かうために。
この部屋に自由な出入りを許している人間は少ない。私がシャワーを浴びている間に訪れたであろう番犬は、この場で主人を待つよりも気を利かせて早々に立ち去ることを選んだらしい。
「相変わらず有能だな」
ボトルを開け、乾いた喉を潤しながら書類の束に目を通す。たまに大雑把な部分が顔を覗かせることもあるが、仕事の早さにおいて彼に勝る者は少なくともこのハウス内には存在しない。
目を通し終えた紙束をテーブルに戻し、ボトルを手にしたまま窓の外に目を向ける。ガラスの向こう側の世界は、オレンジの光に満たされていた。
この一瞬だけを切り取るのならば、早朝にも同じ光景を見ることはできる。だが、私は夜へと変わるこの時間の方が好きだ。オレンジ色の後に訪れる白く清浄な陽の光は、私には眩しすぎるのだから。
「……ふっ」
人知れず笑みを漏らし、ボトルの中身を飲み干した。今夜もまた闇に紛れ、ビジネスの場へと向かうために。
Apr.10 Eiji
「……やりやがった」
俺の盛大なため息が洗面所に響いた。出勤前のクソ忙しい時間だというのに、目の前には頭を抱えたくなる光景が広がっている。
全開の蛇口から景気良く洗面台に向かって流れ落ちる大量の水と、その水をザバザバ浴びて見るも無残な姿になった電動シェーバー。一縷の望みをかけて一応スイッチを入れてはみたが、当然のようにうんともすんとも言いやしない。
「よう、相棒。これはあれか? 朝メシが遅れた腹いせか?」
壊れた電気シェーバーを手に見下ろすと、デンと寝そべる黒猫がいる。太々しく一声上げたその猫は、大あくびをして洗面所を出て行った。
「ったく、図体ばかりでかくなりやがって、中身は悪ガキのままじゃねぇか」
そう毒づいてみたところで、この状況が変わるわけでもない。仕方なく洗面台の棚を漁ってみると、使いかけのシェービングフォームとカミソリを見つけた。シェービングフォームを最後に使ったのがいつだったか覚えてもいないが――。
「まあ、死にはしねぇだろ」
とにかく今は時間が惜しい。さっさとフォームを塗って、手早くカミソリの刃を滑らせる。カミソリで髭を剃るのはだいぶ久しぶりだが、感覚は鈍っていないようだ。
「こんなもんか」
カミソリを置いてフォームを洗い流す。そして俺は前言撤回する羽目になった。鏡には綺麗さっぱり剃り残すことなく髭を剃り終えた俺がいる。どうやら普段は残すところまで剃り落としてしまったらしい。
「あいつに絶対つっこまれるな……」
俺はまた一つ、盛大なため息をついた。
俺の盛大なため息が洗面所に響いた。出勤前のクソ忙しい時間だというのに、目の前には頭を抱えたくなる光景が広がっている。
全開の蛇口から景気良く洗面台に向かって流れ落ちる大量の水と、その水をザバザバ浴びて見るも無残な姿になった電動シェーバー。一縷の望みをかけて一応スイッチを入れてはみたが、当然のようにうんともすんとも言いやしない。
「よう、相棒。これはあれか? 朝メシが遅れた腹いせか?」
壊れた電気シェーバーを手に見下ろすと、デンと寝そべる黒猫がいる。太々しく一声上げたその猫は、大あくびをして洗面所を出て行った。
「ったく、図体ばかりでかくなりやがって、中身は悪ガキのままじゃねぇか」
そう毒づいてみたところで、この状況が変わるわけでもない。仕方なく洗面台の棚を漁ってみると、使いかけのシェービングフォームとカミソリを見つけた。シェービングフォームを最後に使ったのがいつだったか覚えてもいないが――。
「まあ、死にはしねぇだろ」
とにかく今は時間が惜しい。さっさとフォームを塗って、手早くカミソリの刃を滑らせる。カミソリで髭を剃るのはだいぶ久しぶりだが、感覚は鈍っていないようだ。
「こんなもんか」
カミソリを置いてフォームを洗い流す。そして俺は前言撤回する羽目になった。鏡には綺麗さっぱり剃り残すことなく髭を剃り終えた俺がいる。どうやら普段は残すところまで剃り落としてしまったらしい。
「あいつに絶対つっこまれるな……」
俺はまた一つ、盛大なため息をついた。
Apr.11 Senna
「う〜ん……今何時……って、うわ……」
枕元に置いて寝たはずのスマホを手探り見つけて、表示された時刻に思わず声が出た。間も無く午後3時。お昼どころかもう夕方だ。
「……まあ、何も予定無いんですけど」
正確には予定が無くなったというのが正しい。
「恨みますからね、周防さん……」
君に緊急呼び出しの電話がかかってきたのは約半日前。珍しく君が土曜日に休みを取れたからと、たまには早起きしてどこかに出かけようとしていた矢先のことだった。
「特広が忙しいのは今に始まったことじゃないですけどー……」
やりどころのない気持ちが悶々と胸の奥に溜まっていく。
「あーあ、退屈」
体を起こしているのも億劫になって、枕に勢いよく顔を埋めた。ちらりと隣に目をやると、朝まで君が着ていたモコモコのパジャマがある。今僕が着ているのと色違いのそれは、いつだったか君が買ってきたものだ。
「あ……」
引き寄せると微かに君の匂いがした。抱きしめたらより強く君の存在を感じる。
「早く帰って来ないかなあ……」
君のパジャマを抱きしめたまま、僕はベッドの上で体を丸めた。
枕元に置いて寝たはずのスマホを手探り見つけて、表示された時刻に思わず声が出た。間も無く午後3時。お昼どころかもう夕方だ。
「……まあ、何も予定無いんですけど」
正確には予定が無くなったというのが正しい。
「恨みますからね、周防さん……」
君に緊急呼び出しの電話がかかってきたのは約半日前。珍しく君が土曜日に休みを取れたからと、たまには早起きしてどこかに出かけようとしていた矢先のことだった。
「特広が忙しいのは今に始まったことじゃないですけどー……」
やりどころのない気持ちが悶々と胸の奥に溜まっていく。
「あーあ、退屈」
体を起こしているのも億劫になって、枕に勢いよく顔を埋めた。ちらりと隣に目をやると、朝まで君が着ていたモコモコのパジャマがある。今僕が着ているのと色違いのそれは、いつだったか君が買ってきたものだ。
「あ……」
引き寄せると微かに君の匂いがした。抱きしめたらより強く君の存在を感じる。
「早く帰って来ないかなあ……」
君のパジャマを抱きしめたまま、僕はベッドの上で体を丸めた。
Apr.12 Gilles
「くそ、やっちまった……」
鏡に映った姿を見て、オレは思い切り舌打ちした。昨夜仕事終わりにシャワーを浴びた後、髪を乾かすのが億劫でそのままベッドに倒れ込んだ。その結果がコレだ。
「……ひでぇな」
頭頂部から前髪にかけて四方八方へと好き勝手に跳ね散らかし、後ろ髪は絡んであちこちにダマができている。芸術的なまでの寝癖を直すのは、なかなかに骨が折れそうだ。
「いっそ切っちまうか」
寝癖直しの手間を考えたら、その方が手っ取り早くていい。元々意識してのばしていたわけでもなかった。放っておいたら今の長さになっただけだ。別に思い入れも何もない。
「あー、でもな……」
尻ポケットのナイフに手を伸ばしかけて動きを止める。
「あいつ、触るの好きだよな、これ」
いつもは一つに括っている後ろ髪をわざわざ解いて、嬉しそうに指を絡ませるアンタの姿がふと脳裏をよぎった。もちろんベッドの中の話だが。――。
「……ま、もう一度浴びりゃいいか」
そしてオレは、着たばかりのシャツを脱いだ。
鏡に映った姿を見て、オレは思い切り舌打ちした。昨夜仕事終わりにシャワーを浴びた後、髪を乾かすのが億劫でそのままベッドに倒れ込んだ。その結果がコレだ。
「……ひでぇな」
頭頂部から前髪にかけて四方八方へと好き勝手に跳ね散らかし、後ろ髪は絡んであちこちにダマができている。芸術的なまでの寝癖を直すのは、なかなかに骨が折れそうだ。
「いっそ切っちまうか」
寝癖直しの手間を考えたら、その方が手っ取り早くていい。元々意識してのばしていたわけでもなかった。放っておいたら今の長さになっただけだ。別に思い入れも何もない。
「あー、でもな……」
尻ポケットのナイフに手を伸ばしかけて動きを止める。
「あいつ、触るの好きだよな、これ」
いつもは一つに括っている後ろ髪をわざわざ解いて、嬉しそうに指を絡ませるアンタの姿がふと脳裏をよぎった。もちろんベッドの中の話だが。――。
「……ま、もう一度浴びりゃいいか」
そしてオレは、着たばかりのシャツを脱いだ。
Apr.13 Ryo
駅の改札を出てすぐ、俺は思い切り顔をしかめた。ざあざあと音を立てて降り注ぐ大粒の雨に、駅前の景色が霞んでいる。
「降らないんじゃなかったのか……?」
家を出る前に確認したスマホの天気アプリでは、確か今日の降水確率は0パーセント、一日中良い天気になると表示されていた。
だが改めてアプリを開いてみると0パーセントだったはずの降水確率が、しれっと90パーセントまで跳ね上がっている。ご丁寧に添えられた「お出かけの際は傘を忘れずに!」の一文がそこはかとなく神経を逆撫でる。
「ついてないな……」
愛車を車検に出してしまったから、今朝は久しぶりに電車で出勤した。殺気立った人混みにも辟易したが、よりにもよって乗っていた電車が途中駅で遅延した。
そして鮨詰め状態の車内からようやく解放されたと思ったら、極め付けがこの大雨だ。ため息の一つもつきたくなる。
「……どうするかな」
駅から港湾厚生局までそれほど距離はない。今この時のためだけにビニール傘を買うのも馬鹿らしい。替えのスーツは置いてあるから、シャワーを浴び直して着替えるのもありだ。「よし、行く――」
雨の中へ一歩踏み出そうとした時、駅前の大通りを見覚えのある派手な赤いスポーツカーが横切った。通勤時間帯の街に不似合いなエンジン音をたてて遠ざかるその車の運転手が、これまた見覚えのあるうざったい長髪の男だとわかると、俺の苛立ちは頂点に達した。
「降らないんじゃなかったのか……?」
家を出る前に確認したスマホの天気アプリでは、確か今日の降水確率は0パーセント、一日中良い天気になると表示されていた。
だが改めてアプリを開いてみると0パーセントだったはずの降水確率が、しれっと90パーセントまで跳ね上がっている。ご丁寧に添えられた「お出かけの際は傘を忘れずに!」の一文がそこはかとなく神経を逆撫でる。
「ついてないな……」
愛車を車検に出してしまったから、今朝は久しぶりに電車で出勤した。殺気立った人混みにも辟易したが、よりにもよって乗っていた電車が途中駅で遅延した。
そして鮨詰め状態の車内からようやく解放されたと思ったら、極め付けがこの大雨だ。ため息の一つもつきたくなる。
「……どうするかな」
駅から港湾厚生局までそれほど距離はない。今この時のためだけにビニール傘を買うのも馬鹿らしい。替えのスーツは置いてあるから、シャワーを浴び直して着替えるのもありだ。「よし、行く――」
雨の中へ一歩踏み出そうとした時、駅前の大通りを見覚えのある派手な赤いスポーツカーが横切った。通勤時間帯の街に不似合いなエンジン音をたてて遠ざかるその車の運転手が、これまた見覚えのあるうざったい長髪の男だとわかると、俺の苛立ちは頂点に達した。
Apr.14 Rei
ラボに着いてすぐブラインドを上げると、眩しいほどの光が室内に差し込んできた。ガラスの向こうには、昨日の大雨が嘘みたいな青空が広がっている。
こういう日は気分も良い。鼻歌混じりにエスプレッソマシンのスイッチを入れ、ジャケットを脱いで白衣を羽織る。そうしているうちにラボは良い匂いに満たされた。
「今日は5件か」
比較的少ない鑑定依頼に目を通しながら、淹れたてのエスプレッソに口をつける。口内に程よい苦味と香ばしい匂いが広がった。
「ん……。やっぱり職場で飲むコーヒーは美味しくなきゃダメだよねえ」
基本的に港湾厚生局のどの部署にもコーヒーマシンは置いてあるけれど、そこにかける予算は無いとばかりに備え付けのコーヒー豆は質より量が優先されている。もちろんお世辞にも美味しいとは言えない。
だから鑑定課に配属されてすぐに、オレは最上位モデルのエスプレッソマシンを購入した。それ以来、コーヒー豆もお気に入りのカフェや専門店から仕入れている。当然全てオレの実費だけど、1日の大半を過ごす職場の環境整備は大切だ。それを考えたら大した出費じゃない。
「はいはーい?」
二口目を口に含んだ時、ドアがノックされた。返事をしてすぐに現れたのは、爽やかな朝には不似合いなほどの仏頂面。
「やあ、おはよう真壁。ずいぶん機嫌悪そうだね。何か嫌なことでもあった?」
「……別に何もない」
「あ、そう。それ鑑定依頼? ならそこに適当に置いといて」
「ああ」
真壁はスタスタとオレのデスクに歩み寄ると、手にしていた書類をバサっとおいてそのままラボを出ようとした。そこでふと、オレはあることを思い出す。
「そういえばキミ、昨日ずぶ濡れで出勤して来たけど車はどうしたのさ? もしかしてヘマしてどこかにぶつけでもした?」
途端に真壁の動きが止まる。そしてツカツカと靴音を立てて近づいてきたかと思うと――。
「痛っ?!」
突然、後ろ髪を引っ張られた。
「ちょっと! いきなり何してくれるのさ!?」
理不尽な暴力に抗議の声を上げると、真壁は「車検中だ」と一言だけ残して去って行った。
なぜ髪を引っ張られたのか、オレにはまったくわからない。
こういう日は気分も良い。鼻歌混じりにエスプレッソマシンのスイッチを入れ、ジャケットを脱いで白衣を羽織る。そうしているうちにラボは良い匂いに満たされた。
「今日は5件か」
比較的少ない鑑定依頼に目を通しながら、淹れたてのエスプレッソに口をつける。口内に程よい苦味と香ばしい匂いが広がった。
「ん……。やっぱり職場で飲むコーヒーは美味しくなきゃダメだよねえ」
基本的に港湾厚生局のどの部署にもコーヒーマシンは置いてあるけれど、そこにかける予算は無いとばかりに備え付けのコーヒー豆は質より量が優先されている。もちろんお世辞にも美味しいとは言えない。
だから鑑定課に配属されてすぐに、オレは最上位モデルのエスプレッソマシンを購入した。それ以来、コーヒー豆もお気に入りのカフェや専門店から仕入れている。当然全てオレの実費だけど、1日の大半を過ごす職場の環境整備は大切だ。それを考えたら大した出費じゃない。
「はいはーい?」
二口目を口に含んだ時、ドアがノックされた。返事をしてすぐに現れたのは、爽やかな朝には不似合いなほどの仏頂面。
「やあ、おはよう真壁。ずいぶん機嫌悪そうだね。何か嫌なことでもあった?」
「……別に何もない」
「あ、そう。それ鑑定依頼? ならそこに適当に置いといて」
「ああ」
真壁はスタスタとオレのデスクに歩み寄ると、手にしていた書類をバサっとおいてそのままラボを出ようとした。そこでふと、オレはあることを思い出す。
「そういえばキミ、昨日ずぶ濡れで出勤して来たけど車はどうしたのさ? もしかしてヘマしてどこかにぶつけでもした?」
途端に真壁の動きが止まる。そしてツカツカと靴音を立てて近づいてきたかと思うと――。
「痛っ?!」
突然、後ろ髪を引っ張られた。
「ちょっと! いきなり何してくれるのさ!?」
理不尽な暴力に抗議の声を上げると、真壁は「車検中だ」と一言だけ残して去って行った。
なぜ髪を引っ張られたのか、オレにはまったくわからない。
Apr.15 Arlen
「だいぶ汚れていたな……」
黒ずんだ指先に思わず苦笑が漏れる。その汚れはテーブル上の愛銃がもたらしたものだ。オートマチックに比べてリボルバーはさほど手入れを必要としないが、それでも最後にしたのがいつだったかすぐに思い出せない程度には手入れを怠っていた。
ここ最近少しばかり多忙な日々を送っていたとはいえ、武器としてこれを持ち歩いている以上、その威力を自らの手で落とすような真似は実に愚かしい。
「あまり良い傾向ではないな」
自戒を兼ねて言葉にする。その時、部屋のドアがノックされた。
「入れ」
ノックに次いでかけられた声で来訪者を察すると、ホルスターに戻しかけた愛銃を手に、私は椅子から立ち上がった。右腕を伸ばし、銃口をドアへと向ける。私がハンマーを起こしたのと、ドアが開いたのはほぼ同時だった。
「Freeze」
私の発した声に、来訪者――ジルが文字通り硬直する。
「冗談だ。ちょうど手入れを終えたところでね、照準の確認をしたくなった」
「……勘弁してください」
銃を下ろし今度こそホルスターにしまうと、ジルは大げさに肩をすくめて見せる。
「とうとうお払い箱かと思いましたよ」
「おや、何か思い当たる節でも?」
「いえ、何も。それよりこれを。ハウスマネージャーからです」
ジルは早々に話を切り上げると、国際便で送られてきたらしい木箱をテーブルに置く。
「コルトン・シャルルマーニュか。……ほう、なかなかの年代物だな。そういえば最近ハウスマネージャーが新しいバイヤーと契約したと言っていたな」
「試しに一本、ってとこですか」
「まあ、そんなところだろう」
そう言って、私は開けたばかりの木箱を閉じた。
「ジル、これは君が飲むといい。生憎と白ワインはあまり飲まないものでね」
「……いいんですか?」
「質の悪い冗談の詫びだ。いらなければディーラー達にでも振る舞ってやるといい」
「いえ、いただきます」
ジルは一瞬怪訝な顔をしたものの、木箱ごとワインを受け取った。
「用件はそれだけかな?」
「はい」
「ではもう行っていい」
「Yes,sir」
いつも通りの軽い返事をして、ジルが踵を返す。
「ああ、そういえばジル。最近ハウス内で起きている小さな怪奇現象を知っているかな?」
「はい?」
退室の寸前で呼び止めると、長い後ろ髪を揺らしてジルが振り返る。突然何を言い出すんだとでも言いたげな表情だ。私は意図して口角をつり上げると、椅子に腰を下ろした。
「どうもハウス内のワインセラーに保管しておくと、時々上客用のヴィンテージワインがひとりでに消えるようでね。君もせっかくのワインを失わないよう早めに飲むといい。それだけだ。もう行っていい」
「……Yes,sir」
去り際のジルの顔が微かに引きつっていたことを確認して、私は笑みを崩さずゆったりと足を組んだ。
黒ずんだ指先に思わず苦笑が漏れる。その汚れはテーブル上の愛銃がもたらしたものだ。オートマチックに比べてリボルバーはさほど手入れを必要としないが、それでも最後にしたのがいつだったかすぐに思い出せない程度には手入れを怠っていた。
ここ最近少しばかり多忙な日々を送っていたとはいえ、武器としてこれを持ち歩いている以上、その威力を自らの手で落とすような真似は実に愚かしい。
「あまり良い傾向ではないな」
自戒を兼ねて言葉にする。その時、部屋のドアがノックされた。
「入れ」
ノックに次いでかけられた声で来訪者を察すると、ホルスターに戻しかけた愛銃を手に、私は椅子から立ち上がった。右腕を伸ばし、銃口をドアへと向ける。私がハンマーを起こしたのと、ドアが開いたのはほぼ同時だった。
「Freeze」
私の発した声に、来訪者――ジルが文字通り硬直する。
「冗談だ。ちょうど手入れを終えたところでね、照準の確認をしたくなった」
「……勘弁してください」
銃を下ろし今度こそホルスターにしまうと、ジルは大げさに肩をすくめて見せる。
「とうとうお払い箱かと思いましたよ」
「おや、何か思い当たる節でも?」
「いえ、何も。それよりこれを。ハウスマネージャーからです」
ジルは早々に話を切り上げると、国際便で送られてきたらしい木箱をテーブルに置く。
「コルトン・シャルルマーニュか。……ほう、なかなかの年代物だな。そういえば最近ハウスマネージャーが新しいバイヤーと契約したと言っていたな」
「試しに一本、ってとこですか」
「まあ、そんなところだろう」
そう言って、私は開けたばかりの木箱を閉じた。
「ジル、これは君が飲むといい。生憎と白ワインはあまり飲まないものでね」
「……いいんですか?」
「質の悪い冗談の詫びだ。いらなければディーラー達にでも振る舞ってやるといい」
「いえ、いただきます」
ジルは一瞬怪訝な顔をしたものの、木箱ごとワインを受け取った。
「用件はそれだけかな?」
「はい」
「ではもう行っていい」
「Yes,sir」
いつも通りの軽い返事をして、ジルが踵を返す。
「ああ、そういえばジル。最近ハウス内で起きている小さな怪奇現象を知っているかな?」
「はい?」
退室の寸前で呼び止めると、長い後ろ髪を揺らしてジルが振り返る。突然何を言い出すんだとでも言いたげな表情だ。私は意図して口角をつり上げると、椅子に腰を下ろした。
「どうもハウス内のワインセラーに保管しておくと、時々上客用のヴィンテージワインがひとりでに消えるようでね。君もせっかくのワインを失わないよう早めに飲むといい。それだけだ。もう行っていい」
「……Yes,sir」
去り際のジルの顔が微かに引きつっていたことを確認して、私は笑みを崩さずゆったりと足を組んだ。
Apr.16 Eiji
見慣れた公園のベンチに腰を下ろす。少し前までヒラヒラと花を散らしていた桜の木々も、今ではすっかり葉桜になっていた。
「早ぇな……」
季節の移り変わりにそんな感想を抱くようなったのは、最近になってからだ。俺が歳をとったのか、それとも気づかせてくれる奴が近くにいるからなのか。
「ま、お前のおかげだな」
脳裏に浮かんだ顔にふっと口元を緩め、手にしていたビニール袋からサンドイッチと缶コーヒーを取り出す。待ち合わせ相手との合流にはまだ時間があるから、今のうちに昼飯を済ませてしまおうと近くのコンビニで買って来たものだ。
「……ん?」
缶コーヒーを開け、サンドイッチをかじろうとしたところで足に何かが触れた。ベンチの下を覗き込んでみると、そこにいたのは仔猫だった。
「よう、チビ助。1人なのか?」
どうやら腹を空かせているらしい仔猫は、にゃあにゃあと鳴きながらぶち模様の小さな体を必死に俺の足に擦り付けてくる。この警戒心の無さを見る限り、おそらく近所の人間が餌付けをしているのだろう。
「わかったわかった」
仔猫の猛アピールに根負けして、かじろうとしていたサンドイッチから具のハムを1枚引き抜いた。
「ほら、食べな」
適当な大きさにちぎったハムを足元に置いてやると、仔猫はがっつくように食べ始めた。その姿に微かな懐かしさを覚える。
「あいつもこんなチビだったはずなんだけどな……」
今ではすっかり太々しくなった黒猫を思い出すと、人知れず笑みが漏れる。
「ちゃんと食って、たくましくなれよ?」
指先でトントンと撫でてやると、名前も知らない仔猫はゴロゴロと喉を鳴らした。
Apr.17 Senna
よく晴れた日の昼下がり、見慣れたはずの公園で見慣れない光景が繰り広げられていた。
とっくに葉っぱだらけになった桜の木の下にベンチがある。いつも待ち合わせに使うその場所には、待ち合わせ相手の周防さんが座っていた。ただし1人かと言えば、微妙にそうとも言いきれない。
「何やってるんですか、周防さん……」
声をかけると周防さんは、『それ』を手にしたまま顔を上げた。
「よう、セナ。早かったな」
「早かったなじゃないですよ。人を呼び出しておいて、なに猫と戯れてるんですか……」
そう、周防さんの手の中にいたのは、1匹の仔猫だった。まだ生まれてからそれほど経っていないであろうその仔猫が、『港湾のイーグルアイ』の異名を持つベテランマトリに好き放題じゃれついている様は僕にとってなかなかの衝撃だ。
しかも周防さんの見た目が一歩間違えると――いや、間違えなくても一瞬『その筋の人』にしか見えないから、可愛らしい仔猫とのツーショットがなおさら破壊力を増している。
「お前を待ってる間にちょっとな。どうやら懐かれちまったらしい」
「はあ……」
正直そんな経緯はどうでもよかったりするので、とりあえず僕は周防さんの隣に腰を下ろし、ノートパソコンを開いた。
「依頼されてた件ですけど、なんとか――」
キーボードを叩く指を思わず止める。
「……ねえ、君。邪魔しないでくれる?」
ちらりと横目で見ると、周防さんの手に抱かれまま仔猫がキーボードに前足を伸ばしていた。
「なんとか尻尾掴めましたよ。これが結構大変で――」
仕切り直してまたキーボードを叩くと、僕は再び手を止めることになった。あろうことか仔猫は周防さんの手からするりと抜け出して、完全にキーボードの上に乗っていた。
「だからさ、邪魔しないでくださいって」
ぶち模様の仔猫に真面目に言ってみても、にゃーんと一声返されるだけ。そうこうしている間もパソコンの画面は、キーボードから仔猫の体重分の入力を受け取って、意味不明な文字列を延々と並べ続けている。
「お前と遊びたいんだとよ」
助けを求めようとした相手は、おかしそうに喉の奥で笑って見せるだけ。僕は小さくため息をつく。
「遊びたいって言われても……」
仔猫の扱いなんてよくわからない。ひとまずキーボードの隙間に毛が入り込まないよう、そっと両手で仔猫を持ち上げた。
すると――。
「うわ、あったか。それにフワフワ……」
両の掌を介して伝わってきたのは、思いの外悪くない感触。気づけば僕はそのまま、しばらく仔猫を撫で続けていた。
とっくに葉っぱだらけになった桜の木の下にベンチがある。いつも待ち合わせに使うその場所には、待ち合わせ相手の周防さんが座っていた。ただし1人かと言えば、微妙にそうとも言いきれない。
「何やってるんですか、周防さん……」
声をかけると周防さんは、『それ』を手にしたまま顔を上げた。
「よう、セナ。早かったな」
「早かったなじゃないですよ。人を呼び出しておいて、なに猫と戯れてるんですか……」
そう、周防さんの手の中にいたのは、1匹の仔猫だった。まだ生まれてからそれほど経っていないであろうその仔猫が、『港湾のイーグルアイ』の異名を持つベテランマトリに好き放題じゃれついている様は僕にとってなかなかの衝撃だ。
しかも周防さんの見た目が一歩間違えると――いや、間違えなくても一瞬『その筋の人』にしか見えないから、可愛らしい仔猫とのツーショットがなおさら破壊力を増している。
「お前を待ってる間にちょっとな。どうやら懐かれちまったらしい」
「はあ……」
正直そんな経緯はどうでもよかったりするので、とりあえず僕は周防さんの隣に腰を下ろし、ノートパソコンを開いた。
「依頼されてた件ですけど、なんとか――」
キーボードを叩く指を思わず止める。
「……ねえ、君。邪魔しないでくれる?」
ちらりと横目で見ると、周防さんの手に抱かれまま仔猫がキーボードに前足を伸ばしていた。
「なんとか尻尾掴めましたよ。これが結構大変で――」
仕切り直してまたキーボードを叩くと、僕は再び手を止めることになった。あろうことか仔猫は周防さんの手からするりと抜け出して、完全にキーボードの上に乗っていた。
「だからさ、邪魔しないでくださいって」
ぶち模様の仔猫に真面目に言ってみても、にゃーんと一声返されるだけ。そうこうしている間もパソコンの画面は、キーボードから仔猫の体重分の入力を受け取って、意味不明な文字列を延々と並べ続けている。
「お前と遊びたいんだとよ」
助けを求めようとした相手は、おかしそうに喉の奥で笑って見せるだけ。僕は小さくため息をつく。
「遊びたいって言われても……」
仔猫の扱いなんてよくわからない。ひとまずキーボードの隙間に毛が入り込まないよう、そっと両手で仔猫を持ち上げた。
すると――。
「うわ、あったか。それにフワフワ……」
両の掌を介して伝わってきたのは、思いの外悪くない感触。気づけば僕はそのまま、しばらく仔猫を撫で続けていた。
Apr.18 Gilles
「どうするかな、これ……」
今オレは、一本のワインボトルを前に悩んでいた。
ワインの名前はコルトン・シャルルマーニュ。そこそこ手頃な値段で手に入るものから、数千ドルのヴィンテージまで存在するこの白ワインは、数日前にアーレンから譲り受けたものだ。
それがただの気まぐれであれば、思いがけず手に入った上物のワインを心置きなく味わうところだが、残念なことにオレはこの突然の贈り物を素直に喜べるほど楽観的にはなれなかった。
「これはあれか? 冥土の土産ってやつか……?」
ワインを受け取った時、アーレンはこう言っていた。ワインは早く飲んだほうがいい、ハウス内のワインセラーに保管しているワインが突然消えることがあるから、と。
その怪奇現象の原因に、オレは心当たりがありすぎた。確かに何本も――いや、せいぜい両手の指で足りる程度のごく僅かな本数をくすねたことはある。だがそれも大して高価なものじゃない。ごく、一部を除いては。
「……気付くか、普通?」
ハウス内のワインセラーには、数百本のワインが常備されている。その用途はほとんどが上客の接待用で、正直銘柄や在庫まで把握している奴など誰一人として存在しない。
――と、オレは思っていた。少なくとも、このワインを譲り受けた時、アーレンの意味深な笑みを見るまでは。
「絶対わかってやってるよな、あれは……」
相手の反応を楽しみながら、ジワジワと真綿で首を締めるようなやり方はアーレンがもっとも得意とするところだ。伊達に側近をやってるわけじゃないから、嫌になるほどこの目で見てきている。そうなるともう、答えは一つしかない。
「腹、括るか。……いや、括られるのは首かもしれねーな」
自虐のつもりで口にした言葉が、静かな部屋に虚しく響き渡る。自分で言っておきながら、オレはまったく笑えなかった。
今オレは、一本のワインボトルを前に悩んでいた。
ワインの名前はコルトン・シャルルマーニュ。そこそこ手頃な値段で手に入るものから、数千ドルのヴィンテージまで存在するこの白ワインは、数日前にアーレンから譲り受けたものだ。
それがただの気まぐれであれば、思いがけず手に入った上物のワインを心置きなく味わうところだが、残念なことにオレはこの突然の贈り物を素直に喜べるほど楽観的にはなれなかった。
「これはあれか? 冥土の土産ってやつか……?」
ワインを受け取った時、アーレンはこう言っていた。ワインは早く飲んだほうがいい、ハウス内のワインセラーに保管しているワインが突然消えることがあるから、と。
その怪奇現象の原因に、オレは心当たりがありすぎた。確かに何本も――いや、せいぜい両手の指で足りる程度のごく僅かな本数をくすねたことはある。だがそれも大して高価なものじゃない。ごく、一部を除いては。
「……気付くか、普通?」
ハウス内のワインセラーには、数百本のワインが常備されている。その用途はほとんどが上客の接待用で、正直銘柄や在庫まで把握している奴など誰一人として存在しない。
――と、オレは思っていた。少なくとも、このワインを譲り受けた時、アーレンの意味深な笑みを見るまでは。
「絶対わかってやってるよな、あれは……」
相手の反応を楽しみながら、ジワジワと真綿で首を締めるようなやり方はアーレンがもっとも得意とするところだ。伊達に側近をやってるわけじゃないから、嫌になるほどこの目で見てきている。そうなるともう、答えは一つしかない。
「腹、括るか。……いや、括られるのは首かもしれねーな」
自虐のつもりで口にした言葉が、静かな部屋に虚しく響き渡る。自分で言っておきながら、オレはまったく笑えなかった。


