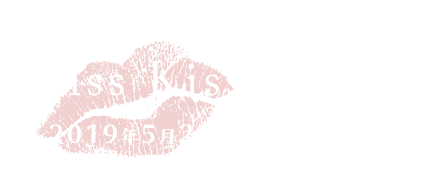Ryo Makabe
「どうした?」
そう問いかける口端が勝手につり上がる。眼前に迫ったお前の表情はどこか悔しげで。堪え切れなくなって俺は小さく噴き出した。
「言い出しっぺがそれでどうするんだよ」
「今日は私からします」なんて、酒が入っているわけでもないのに珍しいことを言うから任せてみたはいいが、お前は俺の膝の上で固まったまま、一向にその先に進まない。――というか進めない。
「ったく」
仕方ないと呟いて、ぐっと首筋に手をかけ引き寄せる。
「あっ」と驚くような声が聞こえたような気もしたが、その小さな声ごとキスで飲み込んだ。
Rei Kurusu
「ね、キスしよっか?」
ソファでくつろぐキミを抱き寄せて、じっと瞳を覗き込む。最初はキョトンとしていた表情が、徐々に焦りとも照れともつかないものに変わっていく。それは試験管の中で薬品の色が移ろう様よりもよほど明白で。
「ね、いいでしょ?」
額に額をくっつけて、より至近距離でキミに問う。もちろん、本気で許しを求めているわけじゃない。キスがしたくなればしたくなった時に、オレは好きにキミの唇を貪る。いつもそうだ。
わざわざこんな質問をしているのは、黙って唇を奪った時よりもこうして言葉にした時の方が、格別に可愛い姿を見せてくれると知っているから。我ながら、なんとも意地が悪い。けれどキミが照れながらも頷いてくれるということも、オレはよく知っている。
「いただきます」
ちゅっと口づけ舌で深く味わうその唇は、やっぱり格別に甘かった。
Arlen Clive
乱れたシーツの波間に身を委ねたまま、隣に横たわる君の髪を撫でる。すると君は私の手を取って、その手のひらに戯れのキスを落とした。
「キスには意味があると知っているか?」
私と目が合うと君は不思議そうに瞬いた。
「手の甲なら尊敬」
今度は君の手を取り、甲にくちづける。
「額の上なら友情、頬の上なら厚意、唇なら愛情、まぶたの上なら憧れ、手のひらなら懇願、腕と首は欲望」
紡ぐ言葉と同じ場所に次々と唇を触れさせる。そうして最後に耳朶に触れた。
「……さて、その他はみな、狂気の沙汰」
君が微かに身を強張らせたのを感じて、思わず笑みが零れた。
「オーストリアの劇作家、フランツ・グリルパルツァーの『接吻』に出てくる有名なセリフだ。いつか君に言ったことがあったな、快楽と狂気は紙一重だと」
再び触れた耳朶は熱を帯び、仄かに色づいていた。
「ルージュエノワールがなくても、つまるところキスもその先の行為も狂気の沙汰というわけだ」
言いながら君を組み敷く。「待って」と焦る唇は、私の唇で黙らせた。さあ、君からの「懇願」を叶えようか。
Eiji Suou
「そういう空気」というのは、いつも突然訪れる。
今もそうだ。互いにソファーに並んで座り、俺は新聞、お前は雑誌を読んでいた。きっかけはたぶん、眠気に軽く目をこすったお前が、俺の肩に頭を預けたこと。
ちらりと目をやれば、意図せずお前と視線が深く絡み合った。途端にリビングの空気が塗り替えられる。どこか甘えるような瞳に誘われて、お前の腰を抱く。引き寄せてその唇を味わおうとした時だった。「なおーん」と一声鳴いたボルが、俺の膝に飛び乗ってくる。
リビングの空気がまた塗り替えられる。甘ったるかったはずのそれはどこかへと吹き飛んで、妙な気まずさだけが残された。
「……お前な」
文句の一つでも言ってやろうと思ったが、当の本人――もとい本猫は俺に背を向けて、「にゃーん」と文字通りの猫撫で声を出した。そして背伸びでもするみたいに、お前の鼻に自分の鼻先をくっつけると、上機嫌にピョンと床に飛び降りて、ちらりと俺を振り返った。
俗に言う猫の「鼻キス」は親愛の証なのだそうだ。つまり、これは飼い猫から俺への宣戦布告ということらしい。
「いい度胸だ、この野郎……」
口にした後、噴き出したお前を見て俺は盛大に後悔した。
Senna Kashiwagi
好きか嫌いかで言われたら、僕は間違いなく「これ」が好きなんだろう。
「ね、もう一回」
君の返事を待たずに、離したばかりの唇をまたくっつける。柔らかくてしっとりとした感触は、何度味わったって飽きることがない。だから終える間際は名残惜しくて、唇を離せばすぐにまた欲しくなる。
「ねえ、もう一回。……いいでしょう?」
ちゅっと音を立ててキスを終え、ねだるように君を見る。すると君は困ったように笑って、「そう言って、もう何時間も経った」と眉を下げる。
「あれ、そうでしたっけ?」
いかにも気づかなかったとばかりにうそぶいて、唇がダメならと頰へ額へ、キスの雨を降らせた。君はくすぐったそうに体を揺らして、小さな抵抗を見せる。それでも本気で拒まれているわけじゃないというがわかってしまうから、たぶん君も「これ」が好きなんだろう。
「じゃあ、もう一回です」
くすくすとつられて笑いながら、僕は一回で終わるはずのないキスを君に贈るのだった。
Gilles Lagrene
寝起きが悪い自覚はある。正直朝は苦手だ。できるなら一生来なきゃいいと、何度思ったことか覚えてもいない。
カーテンを引いた薄暗いベッドルームに、目障りな朝日とやかましいことこの上ない小鳥のさえずりが無遠慮に入り込んでくる。何度寝返りを打ってもそれらを振り払うことはできないと知ると、諦めて受け入れることにした。そのうち、だんだん気にならなくなってくるから不思議だ。
やがて遠のくノイズと入れ違いに、強い睡魔がやって来る。その気配に身を任せ二度寝を決め込もうとした時、別の気配を感じた。
「……あいつか」
無意識に声に出していた。それからほどなく、ドアロックを解除してアンタは部屋に入って来た。時計は見ていないが、おそらく今日も時間通り。優秀なオレの目覚まし時計――もとい、目覚まし役だ。
寝たふりを決め込むオレに、アンタが近づいて来るのがわかる。オレを起こす時、いつもアンタは最初にオレの名前を呼ぶ。それを何度か繰り返して、ダメなら軽く体を揺する。普段はその辺りで起きてやるのだが、今日に限ってちょっとした悪戯心が疼いた。
名前を呼ぶことを諦めて、オレの体に触れようとした瞬間、アンタの手を掴んでベッドの中へ引きずりこむ。何をするんだとばかりに抵抗する両手をシーツに縫い止めて、噛み付くように唇を塞いだ。
「腹減ってんだよ。朝飯に付き合え」
強引なキスから解放されて肩で息をするアンタに、ニヤリと笑いかけてやる。一瞬で「朝飯」の意味を理解したアンタは、そんな時間はないと再び抵抗を試みる。もちろん、捕らえた獲物を逃がすつもりはない。
アーレンに朝の報告に行くまで、あと45分。ゆっくり味わうには短すぎるが、番犬がお行儀良くするのは飼い主の前でだけでいい。せいぜい派手に食い散らかさせてもらおうか。