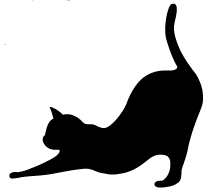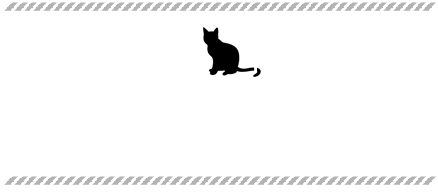最初は鼻先を何かかすめたような気がした。次いでざりざりとヤスリをかけるような独特の感触が訪れ、耳元で鈴の音が小さく鳴る。
「もう少し寝かせろ……」
寝返りを打って頭から布団をかぶると、今度は「なぉーん」と不満そうな鳴き声が聞こえた。無視し続けること数十秒、辺りはようやく静まり返る。
諦めたな。そう思った時だった。
「おぅっ……ふ!?」
突如、腹にかなりの衝撃がくる。我ながらわけのわからん声を上げ飛び起きると、俺の腹に黒くてデカイ毛玉が鎮座していた。
「ボル……てめぇ、俺を殺す気か」
毛玉――もとい、トレーボルという名の黒猫は、実にふてぶてしい態度で俺を見つめている。拾ってきた時はせいぜい手の平大だったというのに、今ではボルの体重は6キロ近い。その重さで勢いよく飛び乗られると、米袋を腹に落とされるようなものだ。
「あー、わかったわかった、飯だな」
また布団をかぶって無視したところで、延々と同じことの繰り返しになるのは目に見えている。諦めてベッドからおりると、キッチンの隅に置いた缶から猫用の皿へ、適当にキャットフードを放り込む。
「ほら、食え」
適量など完全に無視したキャットーフードの山を置くと、ボルはすぐさま食いついた。カリカリカリカリと軽快な音を立てて、瞬く間に山を削っていく。
その様子を眺めながら、もう一度ベッドに戻るべきか悩んだが、結局二度寝は諦めてこのまま起きることにした。
コーヒーでも飲むかと湯を沸かし、その間に郵便受けから朝刊をとる。だが淹れたてのコーヒーを手にリビングに戻ると、そこに俺の居場所はなかった。
「……おい」
ソファーはいつのまにか飯を平らげたボルによって占拠されていた。3人は座れるはずのソファーだというのに、わざわざど真ん中に寝そべっている。ご丁寧に前足から尻尾までピンと伸ばしているせいで、俺が座るスペースは皆無だ。
「はぁ……」
どかすという選択肢もあるにはあるが、面倒になって結局床に腰を下ろした。ボルが占拠したソファーに背中を預け、膝を立てたまま朝刊を開く。
「…………」
コーヒーを片手に文字を追えたのは、ほんのわずかな時間だった。俺と新聞の間にボルが割って入ってくる。そして「撫でろ」とばかりにゴロンと横になって腹を出した。
「お前な……いてっ!?」
黒くフサフサとした腹に触れた瞬間、鋭い痛みが走った。反射的に引っ込めた手には赤い線が残り、眼下ではボルが「しゃー」っと毛を逆立てている。
「この野郎、お前が撫でろって言ったんだろうが!」
思わず声を荒げたが、ボルはさらに毛を逆立て反抗的に俺を睨むばかりだ。だんだん怒鳴った自分が馬鹿らしくなってくる。そして、もっと重要なことに気づいた。
「いけね……」
今のやり取りでコーヒーの中身を床にぶちまけていた。フローリングだったことが不幸中の幸いだが、読みかけの新聞はすでに瀕死だ。仕方なく溢れたコーヒーを新聞に吸い込ませて、ゴミ箱に突っ込む。もう一度淹れ直す気にもなれず、空になったマグカップをシンクに置いた。
そうして再びリビングに戻ってくると、奴の姿がない。
「ボル?」
怒鳴ったせいで拗ねたのだろうかと、いつもボルが逃げ込むソファの下を覗き込んだがそこに黒猫はいない。
「どこに――」
視線をあげると、寝室のドアが少しだけ開いていた。
「ったく、ほんとお前ってやつは……」
ベッドの上で丸まっている黒い塊を目にした途端、全身の力が抜けた。
「好き放題やりやがって、この悪ガキめ」
丸まった身体を撫でてやると、今度は爪を立てられることはなかった。やがてゴロゴロと気持ちよさそうに喉を鳴らす音がする。その音を聞いているうちに、まぶたが重くなるのを感じた。
「……寝るかな」
再びベッドに横になると、ほどなく両脚の間にボルが身を挟む。じんわりと伝わってくる体温を感じながら、俺は静かに目を閉じた。
たまにはこんな休日も悪くない――。
〜fin〜