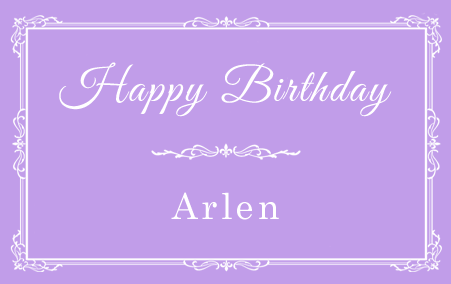はじめに気づいたのは微かな眩さだった。閉じた目蓋の向こう側にそれを感じながら、シーツに手を滑らせる。あるべき所にあるべき存在は無く、仄かな温もりだけが残されていた。
指先でその持ち主の痕跡をひとしきり辿り終えると、私は目を開いた。
「まただな……」
独り言は苦笑から始まった。
君より遅く目覚める朝は、もう何度目になるのだろう。
「これでは昔と完全に逆だ」
二度目の独白にも、やはり苦笑が混じる。
あの頃の私は、深い眠りに落ちることなど許されなかった。
だが今は、当時もっとも遠かったはずの場所に身を置いている。
平穏。それはいつの間にか、私自身に大きな変化をもたらしたのだろう。今でも時折こうして戸惑うほどに。
***
身支度を終えてベッドルームを出ると、芳ばしい香りの立ち込めるダイニングに君の姿があった。
「すまない、どうやら寝坊したようだ」
朝の挨拶より先にそんな言葉が口をついて出ると、コーヒーカップを手に振り返った君はおかしそうに髪を揺らした。もっとゆっくり寝ていてもいいのに、と。
「そういうわけにもいかないさ。君が淹れてくれるコーヒーを飲まなければ、私の一日は始まらないまま終わりを迎えてしまう」
冗談めかして言うと、君は大袈裟だと肩を落とす。
「本当のことだよ」
つられて肩をすくめてから、身を屈めて君の唇に触れる。
「おはよう」
恋人同士の挨拶を終えると、私達はやや遅い朝食の席に着いた。
***
朝食を終え、コーヒーカップの中身も少なくなった頃、君は一度ダイニングを離れすぐに戻って来る。そうして渡されたのは綺麗な包みだった。
「私に?」
君が頷くのを見届けてから、丁寧に包みを開く。中から現れたのは、まったく同じデザインの手袋が二組。私は目を瞬かせ、ふっと口元を緩めた。
「……訂正しなければ。私達に、かな?」
君は微笑みながらメリークリスマスと言うと、ほんの少しだけ躊躇いながらもハッピーバースデーと言葉を続けた。
君が躊躇った理由は、誰よりも私が一番よく知っている。クリスマスもバースデーも、かつて私にとって呪わしい日でしかなかった。その記憶が覆ることはない。あの日止まった時計は、永遠に止まったままなのだから。
だがそれでも――。
「ありがとう……」
思わず君を抱きしめた。今のこの感情を、言い知れぬ愛しさを、言葉になどできはしない。
「大切にするよ」
腕の中の君が柔らかに目を細める。
その表情を前に思う。ああ、いつしか君も変わったのだと。
凛とした白い光は、穏やかな春の陽射しに。貫くような真っ直ぐな強さは、包み込むような優しさに。
ただの男と女になってからの私達は、あの頃とはあまりに違っていた。
「ふっ……」
笑みがこぼれた。苦笑ではなく、心から自然と溢れ出た穏やかな笑みだった。
寄り添ったままの君が不思議そうに私を見ている。なんでもないと、君の額に軽いキスを落とした。
「彼に会いに行こうか」
純白のカサブランカを手に、純白の雪が降り積もるあの場所へ。
最愛の君と手を繋いで――。
〜fin〜