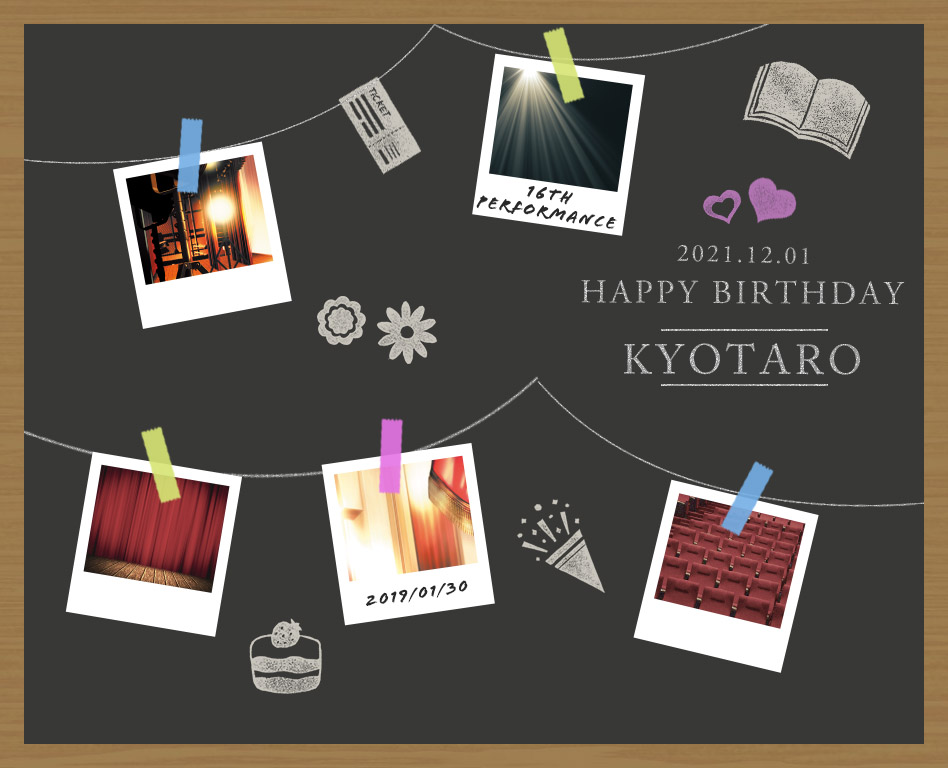『出会い、そして』本条恭太郎 2021年バースデーSS
一目惚れではなかった、と思う。
劇団ラグナロクの新規劇団員オーディションの日。
会場である稽古場にはおおよそ50人ほどが集まっていた。
面接、特技のアピール、そして簡単な実技。
初めてでガチガチに緊張している役者、以前オーディションを落ちているにも関わらず何度も挑戦してくれる役者――。
たとえ巧みな芝居をする者だろうと、そのとき劇団が求めているタイプでなければ落とすこともある。
残念ながらうちのような小さな劇団では、抱えられる劇団員の人数に限りがあるのだから。
「次の人」
「はい!」
呼ばれて進み出た女優は、目に見えて緊張しているパターンだった。
手元の履歴書に目を落とすと、芝居歴は1年とある。
(社会人になってから芝居を始めたのか)
うちのオーディションを受けるのは、学生時代から芝居にどっぷり浸かっている役者が多いから、経験という面で彼女は若干のハンデを負っていることになる。
「志望動機をお願いします。なぜうちの劇団を?」
話を向けると、彼女はひとつ呼吸を置いてから話し始めた。
滑舌が甘い。声量に乏しい。こればかりは経験が物を言うから仕方がない。
――だが俺は彼女の話に耳を傾けながら、心惹かれるものを感じていた。
昔から演劇が好きだったこと、けれどそれはあくまでも趣味であったこと。
社会人になってから見たラグナロクの公演で衝撃を受けたこと。
そのときに初めて、「舞台の上に立ちたい」と思ったこと。
見る側でなく演じる側として観劇するようになり、演劇に対する感じ方がすっかり変わったこと――
くるくると表情が変わり、目が離せない。
声音からも仕草からも、彼女の溢れるような情熱が伝わってくる。
何よりも印象的だったのは、その眼差しだった。
キラキラと輝いて、眩しいほどの――
「……わかりました。面接はこれで終了です」
「ありがとうございました!」
椅子から立ち上がり、丁寧に頭を下げる。
退出する彼女を見送ってから、俺はチェックシートに◎の印をつけた。
* *
実技は、事前に渡してある台本の一部を実際に演じてもらうというものだった。
他の役者の芝居をどう受けるかを見たいため、ラグナロクの役者と掛け合いで演じてもらうことにしている。
彼女の芝居は拙いものだった。
目も当てられない、というほどではないけれど、とてもお客様から代金を頂けるレベルではない。
けれど――
(……やはり、目を惹く)
不思議と彼女の芝居には惹きつけられ、心を動かされるものがあった。
俺はそれが何かを知りたくて、わざと手を叩いて芝居を止める。
「ストップ」
彼女が目を見開き、ハッと振り返った。
「今の台詞、どういう意図で口にした?」
「……え?」
「意図を聞いている」
厳しい口調で問いただすのも、敢えてのこと。
入団すれば、実際の稽古でこれくらい厳しく接することはしょっちゅうある。この程度で心が折れていては、すぐ退団するのは目に見えている。
これも、反応を見たいがための仕掛けだった。そして――俺がこの対応をするのは、見る目のある役者に対してだけ。
彼女は俺に向き直り、真っ直ぐな目で自分の芝居の意図を口にする。
「……君は本当に俺の台本を読んだのか? どこにそんなことが書いてある」
「それは……」
「話にならないな。ここまででいい」
打ち切るように告げ、手元のシートにわざと大きく、×の印を記入する。もちろん、彼女からも見えるように。
「……っ」
これで泣き出してしまう役者も多い。プライドを傷つけられ、ドアを叩きつけるように閉めて出て行く役者も。
もしも彼女がそのどちらかならば、残念だけれどそれまでだったということだ。
けれど――
「……もう一度やらせてください!」
必死に震えを抑えるような声で、彼女が叫んだ。
「……時間の無駄じゃないのか」
「無駄にはさせません」
正直、どこか地味で繊細そうに見えた彼女がそこまでの強さを持っているとは思っていなかった。
予想外の反応に、知らず知らず頬が緩む。
「……わかった。やってみろ」
「ありがとうございます!」
参加しているラグナロクの役者にも頭を下げ、彼女は再び演じ始めた。
先ほどとは違う解釈の芝居を見て、俺は更にこみ上げる笑みを隠すため、頬杖をついた手で口元を覆う。
(……面白いな)
いわば彼女は女優の原石で、磨けば必ず光るとは限らない。
けれど、賭けてみたくなった。彼女の可能性に。
* *
それから1週間後、彼女は晴れてラグナロクの一員となった。
入団してすぐの公演では、裏方として。
そして次の公演で、初めて台詞のある脇役にキャスティングした。
本番はまだまだぎこちなく、ただ勢いだけの芝居ではあったけれど、俺はどこか手応えを感じていた。
そして――
第16回公演、『魔性の女』。
俺はこの公演を転機にしたいと考えていた。自分自身にとっても、劇団にとっても。
看板役者の瀬戸口侑生には過去に演じたことのない役柄を宛がった。
(さて、主人公をどうするか……)
ヒロインの玲香は、これまで俺が書いた芝居の中でも群を抜いて難しい役だ。演技力のある、ベテランの女優に演じさせるのが手堅いところだろう。
けれど、それでは面白くない。
(……手堅さを求める性格なら、最初から演劇なんて先の見えない道を選ぶはずがないよな)
俺は何かに挑む心持ちで、キャスト表の玲香の欄に彼女の名前を打ち込んだ――
* *
――とある出来事をきっかけに、俺は劇団内恋愛を避けてきた。
ラグナロクを旗揚げしてからしばらく経ったとき、当時の看板女優に告白されて付き合い始めた。
知らなかったのは俺だけで、彼女はその頃、当時の看板俳優とも交際していた。彼女は体よく、劇団主宰と看板俳優を二股に掛けたわけだ。
俺たちの関係はすぐに他の劇団員たちに知れ渡り、劇団内にはぎくしゃくとした空気が流れた。
稽古場で劇団員たちが見守る中、俺たちは修羅場を繰り広げ――ラグナロクからは看板俳優と看板女優が同時に退団した。
俺が舞台に立つことでなんとか凌いだけれど、侑生が入団してくれなければラグナロクは立ちゆかなくなっていただろう。
(もうあんな経験は二度とごめんだと思ったのに……)
今、俺の隣には、彼女がいる。
劇団ラグナロクの新しい看板女優として、そしてかけがえのない俺の恋人として。
「…………」
二人揃ってオフの日の昼下がり。
カーテンからは陽射しが差し込み、台本を読みふける彼女の横顔を明るく彩っていた。
「……? どうかしましたか?」
俺の視線が気になったのか、彼女がふと顔を上げる。
「……いや、なんでも」
かれこれ30分以上はそうして見つめていたというのに、ようやく気付いたらしい。
俺に負けず劣らず芝居馬鹿で、一途で真っ直ぐで――堪らなく愛おしい。
「ただ、君が可愛くて仕方ないなと思っていただけだ」
「……!」
途端に彼女の顔が耳まで赤く染まる。
言葉が出てこず口をパクパクさせる様すら可愛らしくて、俺は彼女を抱き寄せて口づけた。
唇を触れさせるだけでは我慢できなくて、次第にキスが深くなる。
キスの合間に漏れる吐息が熱を帯び――
唇を離したときには、彼女の目はしっとりと潤んでいた。
「……ホン読み、まだ続けるのか?」
わざと意地悪く囁けば、彼女はその目で俺を軽く睨む。もちろん、そんな色っぽい顔で睨まれてもまったく怖くないどころか、逆効果だ。
俺は返事を待たずに彼女の手から台本を取り上げてテーブルに置くと、その身体をソファへと押し倒した。
――人生、何が起きるかわからない。芝居も、彼女との出会いも。
一目惚れではなかったはずの彼女にいつの間にか惹かれ、こうして生活を共にして。
できるならばこの先もずっと、一緒にいたいと思っている。
あの日、彼女がラグナロクのオーディションを受けなければ、俺たちは出会うことはなかった。
あの日、俺が彼女を落としていれば、俺たちの関係はそれきりだった。
いくつもの『もしも』の先に、今の俺たちがいる。
奇跡のような関係だからこそ、大切にしていきたい。
決して壊さないように——俺のすべてを賭けて。
——Dear Kyotaro,Happy Birthday!